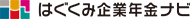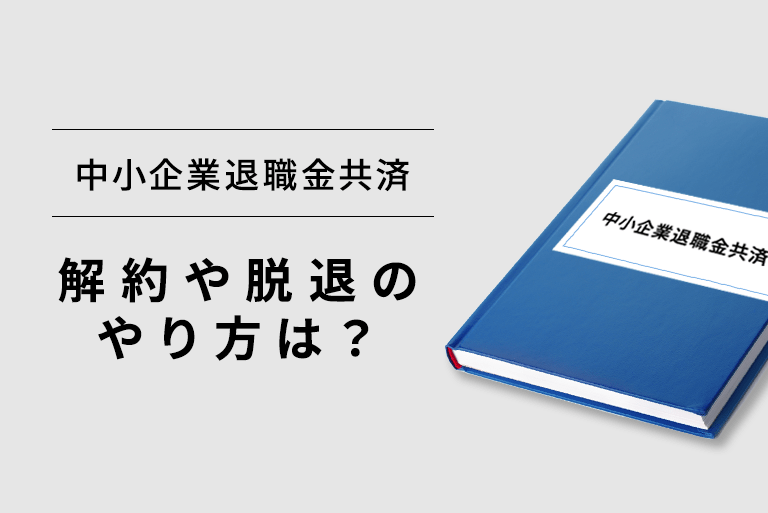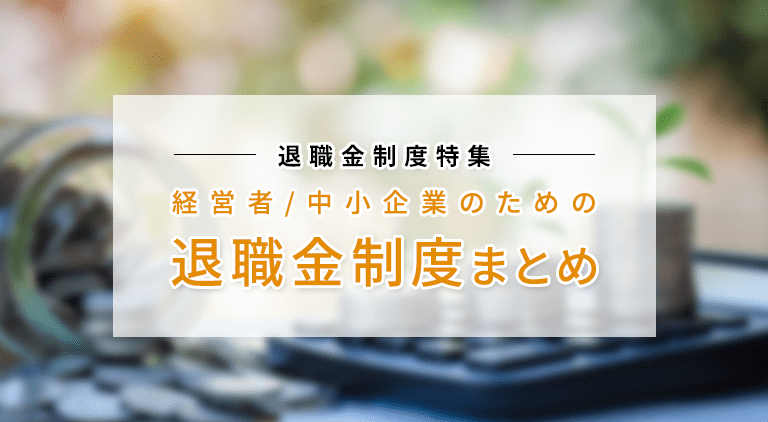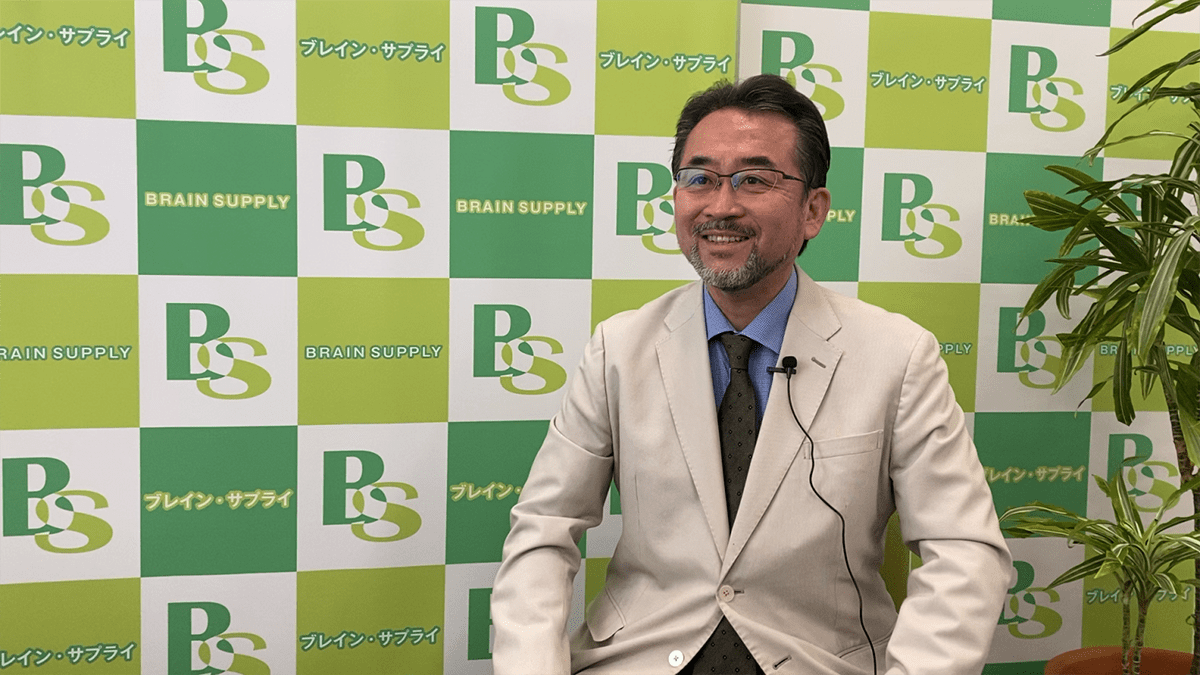事業がまだ安定していない中小企業にとって、「中小企業退職金共済(中退共)」は、メリットの大きい制度です。
しかしときにはメリット以上に負担が大きくなり、中小企業退職金共済(中退共)を途中解約しなくてはいけないケースもあるでしょう。
結論からいって、中小企業退職金共済(中退共)を途中でやめることは、可能です。そこで本記事では、中小企業退職金共済(中退共)の解約・脱退方法を解説します。
解約後の積立金の取り扱いについてもまとめているので、中小企業退職金共済(中退共)の途中解約をご検討されている方は、ぜひご一読ください。
なお中小企業退職金共済(中退共)に関する概要は、こちらの記事で解説しています。
※こちらのコンテンツは、中小企業退職金共済事業本部Webサイトを参照のうえ、作成しています。
- 退職金制度の導入や乗り換えをご検討の方へ
- 中小企業を中心に、導入が増えている注目の企業年金・退職金制度「はぐくみ企業年金」。 福利厚生の充実だけでなくコスト削減効果も期待できるなど、従業員、経営者、会社それぞれにメリットが生まれるとても人気の制度です。>>詳しくはこちら
目次
中小企業退職金共済(中退共)の解約条件
中小企業退職金共済(中退共)の解約には、以下『1』の条件、もしくは『2』の条件の「いずれか」を満たす必要があります。
【中退共の解約の条件】
- 解約について従業員の同意を得られている
- 厚生労働大臣から認定を受ける
中小企業退職金共済(中退共)は、事業主の判断のみでは原則解約ができません。基本的には、従業員の同意を得たうえでの解約手続きが望ましいでしょう。
しかしときには、「早急な解約が必要な状況だが、従業員の同意を得られない」ケースも考えられます。このような場合の救済策として利用できるのが、『2』の条件です。
厚生労働大臣から「掛金納付の継続が困難」だと認められた場合には、従業員の同意を得られないケースであっても、中小企業退職金共済(中退共)の解約が可能となります。
中小企業退職金共済(中退共)の解約手続きの種類と方法
中小企業退職金共済(中退共)の解約手続きは、「従業員の同意が得られた場合」と、「同意が得られず厚生労働大臣の認定を受ける必要がある場合」の2種類で、方法が大きく異なります。
ここでは、ケース別に手順を解説します。自社に当てはまる方法をご確認ください。
①従業員の同意が得られて解約(共済契約の解除)したい場合
中小企業退職金共済(中退共)の途中解約について、従業員に周知をし同意を得られた場合には、以下2点の書類を「中退共本部契約課」まで郵送します(送付先はこちらのページを参照ください)。
【中退共の解約に必要な書類】
- 退職金共済契約解除通知書
- (途中解約に関して)従業員の同意を得ていることが分かる書面
各書類に不備がなければ、中小企業退職金共済(中退共)の途中解約が認められます。
なお、契約解除日は、中退共本部契約課に「退職金共済契約解除通知書」が到着した日です。書類到着前を契約解除日として定めることはできないため、途中解約を希望している場合は、なるべく早めの郵送が望ましいでしょう。
必要書類の準備方法および注意点
退職金共済契約解除通知書については、契約時に送付されている「退職金共済契約関係書類綴」内にあります。もしもこちらを紛失している場合には、「手続様式見本集」(外部リンク)からダウンロードが可能です。
従業員の同意を得ていることが分かる書面については、電子メールによる通知およびその返信内容を印刷する方法が推奨されます。
ただし同意書として認められる条件は詳細に定められているため、以下すべて漏れがないようにご注意ください。
【事業主から従業員への通知メールについて】
- 従業員の名前(フルネーム)
- 従業員の被共済者番号
- 事業所、もしくは個人事業主名(フルネーム)
- 中小企業退職金共済の途中解約に関する通知
- 途中解約に対する意思表示の引用返信が必要であることの通知
【従業員から事業主への引用返信メールについて】
- 従業員の名前(フルネーム)
- 事業所、もしくは個人事業主名(フルネーム)
- 途中解約に対する同意の意思表示文
【メールの印刷方法について】
- 通知メールと引用返信メールの内容がすべて確認可能であること(単独で印刷したものは不可)
- 受信者と送信者のメールアドレスが表示されていること
各書類の書き方について詳しくは、こちらのページ(外部リンク)もご覧ください。
②掛金納付の継続が困難であるため解約(共済契約の解除)をしたい場合
「掛金納付の継続が困難であるが、従業員の同意を得られない」場合には、まず「中退共本部契約課」(外部リンク)まで、問い合わせます。
厚生労働大臣の認定申請を受ける手順について、詳しい説明を受けられます。
中小企業退職金共済(中退共)を解約した場合、これまでの積立金はどうなるのか?
中小企業退職金共済(中退共)の積立金は、解約時点で掛金の納付期間が12ヵ月以上ある従業員に対して、「解約手当金」として支給されます。
支給額は、以下のとおり納付月数に応じます。
【納付期間に応じた支給額の目安】
- 納付期間が12ヵ月未満…支給なし
- 納付期間が12ヵ月以上24ヵ月未満…支給あり(※掛金総額を下回る)
- 納付期間が24ヵ月以上42カ月未満…支給あり(※掛金総額の100%)
- 納付期間が43ヵ月以上…支給あり(※掛金総額を上回る)
なお支給には、従業員本人による請求が必要です。
助成金(掛金助成)を受けた場合は注意!
以上のように中小企業退職金共済(中退共)は途中解約した場合でも、掛金月額と納付月数に応じた額を解約手当金として従業員が受け取れます。
ただし中小企業退職金共済(中退共)の新規加入や、掛金月額の増額をする際に「掛金助成制度」を利用していた場合には、通常よりも解約手当金が減額されるため、ご注意ください。
減額金は、以下2種類の方法により算出された額のうち、より少ない額で算出されます。
【解約手当金の減額金の算出方法】
- 掛金月額×納付月数-掛金助成金相当額
- 解約手当金額×0.70
このように中小企業退職金共済(中退共)の途中解約は、従業員にとって不利益となるケースがあります。企業に対する不信感を高める恐れもあることから、安易な解約は避けるのが無難でしょう。
また中小企業退職金共済(中退共)の途中解約を決めた場合には、詳細な周知に努める他、新しい退職金制度の導入をはじめとした、なんらかの対策のご検討をおすすめします。
事前にチェック! 他の退職金制度との比較
中小企業が退職金制度として取り入れやすい「中小企業退職金共済(中退共)」、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」、「はぐくみ企業年金(確定給付企業年金型の退職金制度)」の3種を比較しました。 基金が資産を運用 運用成績により変動しない
はぐくみ企業年金
企業型確定拠出年金
中小企業退職金共済
根拠法
確定給付企業年金法
確定拠出年金法
中小企業退職金共済法
任意加入
可能
可能
全員加入
加入年齢
70歳未満
70歳未満
制限なし
加入制限
役員も拠出可
役員も拠出可
役員は拠出不可
税制優遇
有り
有り
有り
社会保険料
軽減可 (※1)
軽減可 (※2)
軽減不可
掛金拠出
会社の実質的な負担を抑制 (※1)
会社が負担 (※2)
(会社負担分は損金計上可)
会社が負担
(会社負担分は損金計上可)
拠出金
上限/月
1,000円~給与の20% (上限40万円)
1,000円~55,000円
※iDeCoと併用の場合、上限額が変わります
5,000円~30,000円の16段階 (※3)
運用
加入者が資産を運用
機構(※4)が資産管理・運用
受給額
運用成績により変動しない
運用成績により変動する
受取り
一時金又は年金/
退職時、休職時、
育児・介護休業時にも受取り可能
一時金又は年金/
但し、原則60歳以上に制限
一時金又は分割払い/
退職後に受取り可能
※2:「選択制」を採用した場合、軽減できることがあります。
※3:パートタイマーなど短時間労働者の場合、特例掛金月額として2,000円から可能になります。
※4:ここでは「独立行政法人 勤労者退職金共済機構」のことを「機構」といいます。
確定拠出年金やはぐくみ企業年金との違い
支給時期が実質老後となる確定拠出年金(企業型確定拠出年金を含む)に対し、中小企業退職金共済(中退共)は退職時です。退職金制度として運用するのであれば、中小企業退職金共済(中退共)が使いやすいといえます。
ただし中小企業退職金共済(中退共)は、「加入対象者が従業員のみ」、「従業員全員の加入が必須」といった点は注意が必要でしょう。
企業型確定拠出年金(企業型DC)やはぐくみ企業年金については、以下の記事も参照ください。
参考リンク
他の制度や選択肢は? おすすめ退職金制度のご案内
こちらの記事で、中小企業退職金共済(中退共)以外の選択候補となる、おすすめの退職金制度を紹介しています。合わせてご確認ください。
おすすめは「はぐくみ企業年金」
はぐくみ企業年金は、現在、導入企業や加入者が急増している注目の企業年金・退職金制度です。
選択制などの制度設計により、会社負担を少なく始められるなど、従業員、経営者、会社それぞれにメリットが生れるとてもおすすめの制度です。
まとめ記事で11の選択肢を紹介
こちらのまとめ記事で、退職金制度の選択肢を11件まとめて紹介しています。
他の制度のメリットやデメリットを体系的に比較・検討することができます。
※こちらの記事は2023年1月23日時点の情報を参照の上、執筆しております。
※更新日:2024年12月/記事監修日:2024年12月17日
※当サイトからの外部参照サイト(リンク先サイト)の内容については、当サイトは責任を負いませんので予めご了承ください。