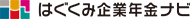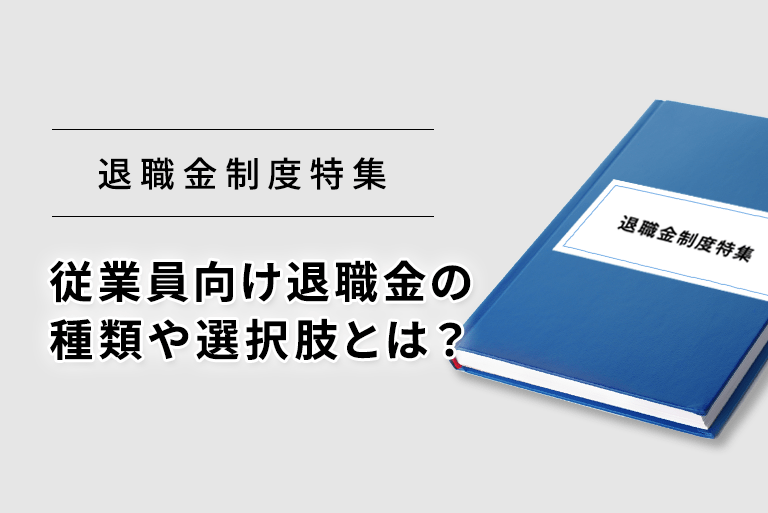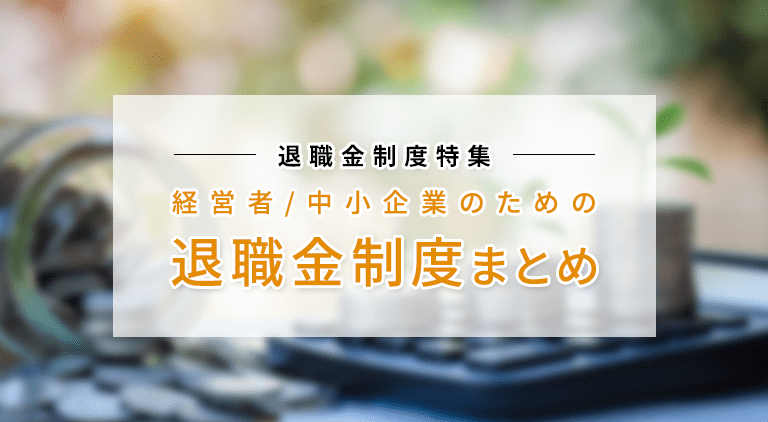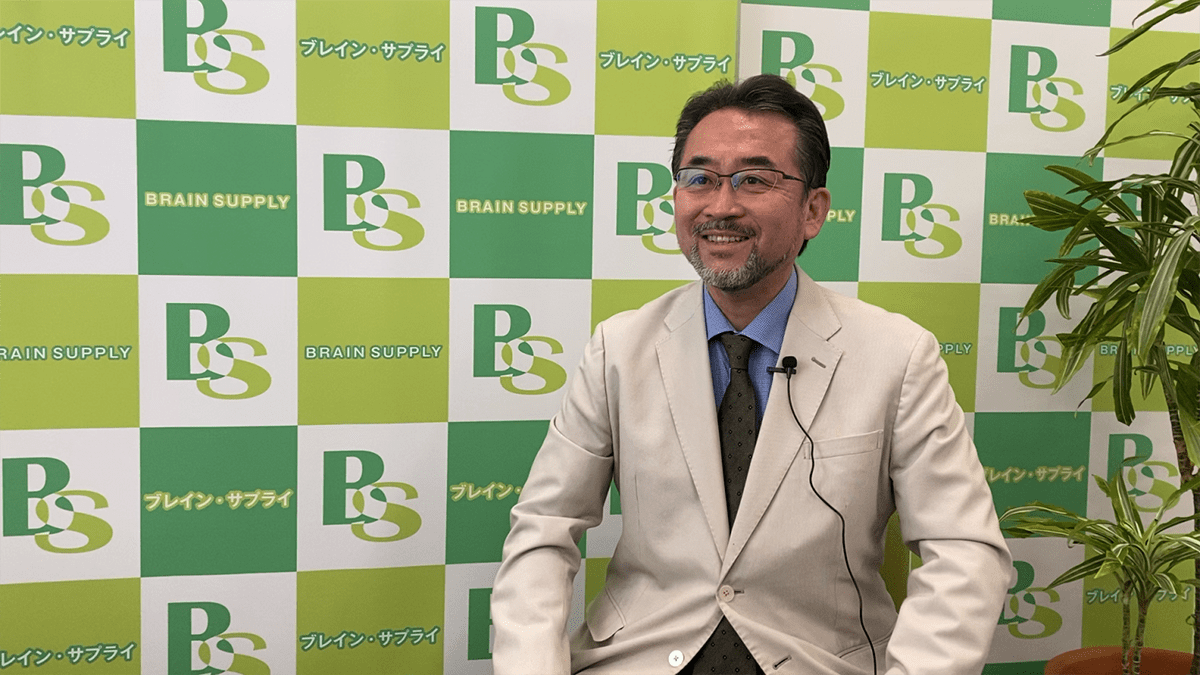従業員の福利厚生を充実させようと考えたとき、「退職金」の導入を検討する企業は少なくないでしょう。退職金は従業員に対して非常にメリットが大きい福利厚生であるため、優秀な人材の確保および離職率の低下によく貢献してくれるためです。
しかし退職金制度を運用する際には、まとまった費用が継続的にかかります。制度設計は慎重にならざるを得ないでしょう。
そこで本記事では、従業員向けの退職金制度(または退職金用の共済)には具体的にどのような種類があるのかをまとめました。そのうえで制度の選び方や、おすすめの制度についてもご紹介します。
ご一読いただければ、自社に合った退職金制度の選択ができるようになるでしょう。退職金の導入について悩まれている総務担当者や人事担当者、経営層の方はぜひご覧ください。
- 退職金制度の導入や乗り換えをご検討の方へ
- 中小企業を中心に、導入が増えている注目の企業年金・退職金制度「はぐくみ企業年金」。 福利厚生の充実だけでなくコスト削減効果も期待できるなど、従業員、経営者、会社それぞれにメリットが生まれるとても人気の制度です。>>詳しくはこちら
目次
従業員の福利厚生などが目的? そもそも何のために「退職金」を導入するのか?
具体的な検討に入る前に、まず重要なことは、退職金を支払う目的の確認です。
そのためにも、以下の2点について改めて確認しましょう。
①将来的及び継続的な負担を想定しているか?
賃金の後払い的な性格を持つ退職金は、企業としていったん制度を導入すると、将来にわたって負担が継続し続けます。賞与のように、業績によって支給額を変動させるようなことはできません。
また、昨今は「同一労働同一賃金」の観点から、正社員にのみ退職金を支給し、非正規社員には退職金を支給しないとした場合、その格差の理由が「合理的であるか」というチェックも必要です。
正社員とほとんど変わらない働き方をしているにも関わらず、「契約社員だから」「パートだから」という理由だけで退職金制度の適用外とすることは、違法と判断される可能性があります。
違法と判断されれば、過去にさかのぼって多額の退職金を支払う必要があるほか、将来にわたって、制度発足時には意図しなかった負担ものしかかることになります。
②「人材の確保」などが主要目的になっていないか?
退職金制度導入の目的として、「人材確保のため」「人材の定着のため」「長期にわたる会社への貢献に報いるため」「社員の退職後の生活保障のため」などの理由が挙げられます。
しかし、その目的は本当に退職金でなければ達成できないでしょうか。
また退職金制度の検討の際、つい、制度間の損得に目が行きがちですが、制度はあくまでも退職金原資を確保するための「手段」に過ぎません。
まずは、なぜ退職金制度を導入するのかという「目的」を明確にし、そうすれば将来にわたる負担への「覚悟」につながり、「覚悟」が決まれば選択する制度も決めやすくなるでしょう。
従業員の福利厚生向け退職金(共済を含む)は大きく3種類
退職金制度の検討基準として、まずは大まかな種類を把握しましょう。
退職金の種類は大きく分けて3種類です。「企業年金型」「共済型」のほか、内部留保や保険などを用いて積み立てる「自社準備型」があります。
| 種別 | 具体的な退職金制度 | |
|---|---|---|
| 企業年金型 | 確定給付企業年金(DB) |
|
| 確定拠出年金(企業型DC) |
|
|
| 共済型 |
など |
|
| 自社準備型 |
|
|
従業員の福利厚生向け退職金として活用するのであれば、なかでもおすすめなのは企業年金型と共済型です。
自社準備型は、退職者が出る都度、退職金を用意しなければならず、資金繰りに不安を残します。また、企業年金や共済では掛金拠出時に損金算入が認められる一方、自社準備型では退職金支払い時にしか損金算入が認められず、退職者の多寡によって業績が大きく変動します。
法人保険の活用は、一部は従業員向けのもの(保険商品・サービス)もありますが、多くは従業員向けの福利厚生に利用するには不向きといえそうです。
用語解説
「企業年金」とは?
企業年金とは、企業が従業員の退職後の生活のために設ける年金制度のことをいいます。
従業員の退職時にまとめて退職金を支給する方法を「退職一時金」と呼ぶのに対し、退職後数年かけて年金のように支給する方法は「退職年金」と呼ばれます。
一般的に、法律に基づいて実施される退職年金が「企業年金」と呼ばれ、具体的には「確定給付企業年金(DB)」と「確定拠出年金(DC)」の大きく2種類あり、確定拠出年金(DC)はさらに、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と、個人が任意で加入する「個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)」の2種類に分かれます。
また、日本の年金制度は「3階建て」といわれます。1階が全国民が加入する国民年金(基礎年金)、2階が会社員や公務員が加入する厚生年金、そして3階がこの企業年金です。なお、企業年金は公的年金(国民年金や厚生年金)に上乗せして任意で加入する制度であるため、私的年金ともいわれています。
※法律に基づいて実施される退職年金には、他に「厚生年金基金」がありますが、事実上廃止され、新設はできません。
※法律に基づかない、自社独自のルールに基づいて実施される退職年金を「自社年金」と呼ぶこともあります。
「共済」及び「退職共済」とは?
共済とは、複数の人がお金を出し合い、互いに保障や援助を行う仕組みのことをいいます。特に、退職時の一時的な資金需要に備えた共済を「退職金共済」と呼び、加入条件や加入対象が中小企業向けとなっています。
具体的には、「中小企業退職金共済(中退共)」「小規模企業共済」「特定退職金共済」「特定業種退職金共済」「社会福祉施設職員等退職手当共済」などがあります。
なお、「特定退職金共済」と「特定業種退職金共済」は名称が似通っていますが、前者は商工会議所をはじめとした特定退職金共済団体が運営している制度で、後者は建設業や清酒製造業、林業向けの制度で、独立行政法人 勤労者退職金共済機構が運営しています。
従業員の福利厚生向け退職金制度(共済を含む)の主な特徴や違い
ここからは、従業員の福利厚生向け退職金制度としておすすめの「企業年金型」と「共済型」に含まれる主要制度の主な特徴や違いを解説します。
解説では以下5つのポイントに分けて、各種制度を比較しています。
②給付額や資産の運用について
③給付の種類やタイミングについて
④掛金拠出と上限額について
⑤税制メリットについて
すでに希望の制度設計が定まっているケースはもちろん、これから制度設計を固めていくケースでも①~⑤の順に沿って比較することで、自社に合った制度に見当を付けられるでしょう。
なお、従業員は加入対象外ですが、「小規模企業共済」についても合わせてご紹介します。
①加入者や導入企業の制限について
まずは加入者や導入企業の制限について比較し、自社に導入可能な制度を絞りましょう。
| 制度名 | 従業員の加入 | 経営者の加入 |
企業の制限 |
|---|---|---|---|
| ▼企業年金型 | |||
| 確定給付企業年金(DB) | 可能 | 可能 | 原則無し (但し制度にもよる) |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 可能 | 可能 | 原則無し |
| iDeCo+(イデコプラス) | 可能 | 可能 | 有り |
| ▼共済型 | |||
| 中小企業退職金共済(中退共) | 可能 (但し要全員加入) |
加入不可 | 有り |
| 小規模企業共済 | 加入不可 | 加入可 | 有り |
| 特定退職金共済 | 可能 (但し要全員加入) |
加入不可 | 原則無し |
「企業年金型」の制度について
企業年金型の制度は、いずれも従業員だけでなく経営者も加入できます。経営層向けの退職金制度を別途用意するのが困難な小規模企業や中小企業でも導入しやすいでしょう。
また、「確定給付企業年金(DB)」(但し一部の制度を除く)と「企業型確定拠出年金(企業型DC)」は原則、どの企業でも導入できますが、「iDeCo+(イデコプラス)」は、iDeCoへの加入が前提のうえ、DBや企業型DCを導入しておらず、かつ従業員の数が300人以下(※1)でなくてはならないとの要件が定められています。
詳しくは、「iDeCo+(イデコプラス)という選択肢とメリット/デメリット」の記事を合わせて参照ください。
(※1)経営事業所が複数ある場合には、全事業所の合計総数が300人以下であること
「共済型」の制度について
共済型の制度は、企業年金型の制度に比べると加入者要件も事業主要件も厳格です。
「中小企業退職金共済(中退共)」と「特定退職金共済」は従業員のみが加入できる制度です。しかしいずれも従業員全員の加入が必要となるため、全従業員の理解を得られず、思うように導入を進められないケースが懸念されます。
さらに中小企業退職金共済(中退共)では、業種別に従業員数や資本金などの要件まで定められています(※2)。
「小規模企業共済」は小規模企業の経営層のみが加入できる制度です。
ただし企業で加入するのではなく個人での加入となるため、企業としての導入メリットはありません。
(※2)一般業種は従業員300人以下または資本金・出資金が3億円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下、小売業は50人以下または5,000万円以下
②給付額や資産の運用について
つづいて、給付額や資産の運用方法について解説します。
| 制度名 | 給付額 | 資産の運用 | |
|---|---|---|---|
| ▼企業年金型 | |||
| 確定給付企業年金(DB) | 運用成績により変動しない | 外部の運用機関が資産を運用するケースが多い | |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 運用成績により変動する | 加入者が資産を運用 | |
| iDeCo+(イデコプラス) | 運用成績により変動する | 加入者が資産を運用 | |
| ▼共済型 | |||
| 中小企業退職金共済(中退共) | 運用成績により変動しない (但し、給付額は加入期間にもよる) |
機構(※3)が資産運用 | |
| 小規模企業共済 | 運用成績により変動しない (但し、給付額は加入期間にもよる) |
機構(※3)が資産運用 | |
| 特定退職金共済 | 運用成績により変動しない | 外部の運用機関が資産を運用するケースが多い | |
「確定給付企業年金(DB)」「中小企業退職金共済(中退共)」「小規模企業共済」「特定退職金共済」は、「各機構(※3)」や生命保険会社など「外部の運用機関」が資産運用を担っているケースが多く、給付額についても、運用成績によって変動せずに受給できる仕組みや取り決めを採用している制度が多いのが一般的です。
そのため、資産運用を安心してお任せにできるなど、従業員など加入者に好まれやすいのが特徴です。
一方、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「iDeCo+(イデコプラス)」は加入者自身が運用商品を選択しなければならず、運用成績によって給付額が変動します。運用成績がよければ想定以上の給付額になりますが、元本割れの可能性もあります。
運用成績により給付額が変動する退職金制度は、従業員に十分な運用知識がないと魅力的な福利厚生だと捉えてもらえない恐れがあります。
現代日本では十分な運用知識を備えた人材が少ないため、周知および投資教育を徹底するといった企業努力が求められるでしょう。
(※3)ここでは「独立行政法人 勤労者退職金共済機構」または「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」を「機構」といいます
③給付の種類やタイミングについて
さらに、給付の種類やタイミングについて解説します。
これらの選択肢が豊富な制度ほど退職ケースを選ばずに保障を得られるため、従業員にとっては魅力度の高い福利厚生になるでしょう。
| 制度名 | 給付の種類 | 給付時期 | |
|---|---|---|---|
| ▼企業年金型 | |||
| 確定給付企業年金(DB) | 一時金又は年金 | 中途退職後に受取り可能/ 老後に年金としても受取り可能(但し条件有り) |
|
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 一時金又は年金 | 原則60歳以上に制限 | |
| iDeCo+(イデコプラス) | 一時金又は年金 | 原則60歳以上に制限 | |
| ▼共済型 | |||
| 中小企業退職金共済(中退共) | 一時金又は分割払い | 中途退職後に受取り可能/ 退職日に60歳以上など一定の条件満たす場合、分割払いでの受取りも可能 |
|
| 小規模企業共済 | 一時金又は分割払い | 共済解約時に受取り可能/ 解約時に60歳以上など一定の条件満たす場合、分割払いでの受取りも可能 |
|
| 特定退職金共済 | 一時金又は年金又は解約手当金 など ※但し制度による |
中途退職後に受取り可能/ 加入期間10年以上など一定の条件満たす場合、分割払いでの受取りも可能 ※但し制度による |
|
いずれの制度も給付種類としては、一時金だけでなく年金(または分割払い)として給付が可能です。
「確定給付企業年金(DB)」「中小企業退職金共済(中退共)」「小規模企業共済」「特定退職金共済」は、一時金として受け取る場合であれば給付時期を原則選びません。
定年退職に限らず中途退職(※)でも、退職時に給付金の請求が可能になります。
一方、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「iDeCo+(イデコプラス)」は、原則60歳を迎えるまでは給付金の請求が不可です。
そのため、企業型確定拠出年金(企業型DC)やiDeCo+(イデコプラス)の加入者が中途退職する場合、転職先に同様の制度があれば移換手続きが必要です。
同様の制度がない場合には脱退一時金を請求するか、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」に移換するかの選択が必要となるため、このあたりの投資教育も徹底しなくてはいけないでしょう。
(※)小規模企業共済だけは個人向け共済であるため、共済解約時が給付時期となる
補足
近年は転職も含むキャリアパスの構築が活発化していることから、多くの労働者は給付時期の選択肢が豊富な制度に強い魅力を感じると考えられます。
優秀な人材の確保および離職率の低下を導入目的とするのであれば、昨今の労働事情や背景も踏まえた制度選びが重要となるでしょう。
④掛金拠出と上限額について
掛金の拠出方法や上限額について解説します。
これらを比較し、企業のコスト負担が適切であるかを検討しましょう。
| 制度名 | 掛金の負担 | 掛金額の範囲 |
|---|---|---|
| ▼企業年金型 | ||
| 確定給付企業年金(DB) | 会社が負担 | 制度により異なる |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 会社が負担 | 1,000円~55,000円/月 ※iDeCoと併用の場合、上限額が変わります |
| iDeCo+(イデコプラス) | 一部会社側が負担 (会社負担分は損金計上可) |
5,000円~23,000円/月 |
| ▼共済型 | ||
| 中小企業退職金共済(中退共) | 会社が負担 | 5,000円~30,000円/月の範囲で16段階 |
| 小規模企業共済 | 加入者が負担 | 1,000円~70,000円/月の範囲(500円単位) |
| 特定退職金共済 | 会社が負担 | 制度により異なるが、1,000円~30,000円が一般的/月の範囲(1,000円単位) |
「iDeCo+(イデコプラス)」と「小規模企業共済」を除き、いずれも会社が掛金を負担します。
ただし、「確定給付企業年金(DB)」と「企業型確定拠出年金(企業型DC)」については、制度設計によって会社の掛金負担を抑えることもできます。
また、掛金額の範囲は制度によってさまざまですが、下限が低く、企業規模を選ばずに導入しやすいのは「確定給付企業年金(DB)の一部」「企業型確定拠出年金(企業型DC)」「特定退職金共済の一部」です。
なおいずれの制度であっても、会社が負担した掛金はすべて損金として計上できます。
コラム
確定給付企業年金の「はぐくみ企業年金」の場合、掛金は月額1,000円~給与の20%まで可能
「はぐくみ企業年金」(正式名称:福祉はぐくみ企業年金基金)は確定給付企業年金のひとつですが、掛金額の範囲がとても幅広い制度となっています。
掛金の下限が月額1,000円と低く、上限は給与の20%(※別途上限あり)までであるほか、「選択制確定給付企業年金」という制度設計によって、会社の掛金負担を抑えながら制度の導入が可能です。
⑤税制メリットについて
最後に、税制メリットなどについて解説します。
退職金制度のなかには、加入者や企業にとって税制メリットが得られるものもあります。
| 制度名 | 税制優遇 | 法定福利費の軽減 | |
|---|---|---|---|
| ▼企業年金型 | |||
| 確定給付企業年金(DB) | 有り | 制度設計により可能 | |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 有り | 制度設計により可能 | |
| iDeCo+(イデコプラス) | 有り | 不可 | |
| ▼共済型 | |||
| 中小企業退職金共済(中退共) | 有り | 不可 | |
| 小規模企業共済 | 有り | 不可 | |
| 特定退職金共済 | 有り | 不可 | |
各制度とも、退職一時金として受け取る場合には「退職所得控除」、年金受け取りや分割払いでは「公的年金等控除」が適用されたり、小規模企業共済以外の制度では掛金を損金計上できるといった税制優遇があります。
法定福利費の軽減に関しては、「確定給付企業年金(DB)」と「企業型確定拠出年金(企業型DC)」のみが制度設計によっては可能です。
税制メリットを得たいのであれば、こちら2種類から優先して選ぶのがよいでしょう。
コラム
確定給付企業年金の「はぐくみ企業年金」の場合、法定福利費の軽減も期待できます
確定給付企業年金である「はぐくみ企業年金」(正式名称:福祉はぐくみ企業年金基金)の場合、税制優遇以外に「選択制確定給付企業年金」という制度設計によって、法定福利費の軽減効果も期待できます。
詳しくは、下記のリンクよりご確認ください。
※はぐくみ企業年金そのものが法定福利費の負担を軽減させるものではありません。
福利厚生の充実におすすめ退職金制度のご紹介
福利厚生の充実を目的として退職金制度を検討しているのであれば、ぜひ「はぐくみ企業年金」をご検討ください。ここではほかの制度の比較表を基に、はぐくみ企業年金のメリットを解説します。
おすすめは「はぐくみ企業年金」
はぐくみ企業年金は、現在、導入企業や加入者が急増している「確定給付企業年金」型の退職金制度です。選択制などの制度設計により、会社負担を少なく始められるなど、従業員、経営者、会社それぞれにメリットが生れるとてもおすすめの制度です。
(参考記事:はぐくみ企業年金にはどのようなメリットやデメリットがあるのか?)
はぐくみ企業年金と主要制度との比較
基金が資産を運用 運用成績により変動しない
はぐくみ企業年金
企業型確定拠出年金
中小企業退職金共済
根拠法
確定給付企業年金法
確定拠出年金法
中小企業退職金共済法
任意加入
可能
可能
全員加入
加入年齢
70歳未満
70歳未満
制限なし
加入制限
役員も拠出可
役員も拠出可
役員は拠出不可
税制優遇
有り
有り
有り
社会保険料
軽減可 (※1)
軽減可 (※2)
軽減不可
掛金拠出
会社の実質的な負担を抑制 (※1)
会社が負担 (※2)
(会社負担分は損金計上可)
会社が負担
(会社負担分は損金計上可)
拠出金
上限/月
1,000円~給与の20% (上限40万円)
1,000円~55,000円
※iDeCoと併用の場合、上限額が変わります
5,000円~30,000円の16段階 (※3)
運用
加入者が資産を運用
機構(※4)が資産管理・運用
受給額
運用成績により変動しない
運用成績により変動する
受取り
一時金又は年金/
退職時、休職時、
育児・介護休業時にも受取り可能
一時金又は年金/
但し、原則60歳以上に制限
一時金又は分割払い/
退職後に受取り可能
※2:「選択制」を採用した場合、軽減できることがあります。
※3:パートタイマーなど短時間労働者の場合、特例掛金月額として2,000円から可能になります。
※4:ここでは「独立行政法人 勤労者退職金共済機構」のことを「機構」といいます。
まとめ記事で11の選択肢を紹介
こちらのまとめ記事で、退職金制度の選択肢を11件まとめて紹介しています。
他の制度のメリットやデメリットを体系的に比較・検討することができます。
※こちらの記事は2023年7月時点の情報を参照の上、執筆しております。
※更新日:2025年1月/記事監修日:2025年1月31日
※当サイトからの外部参照サイト(リンク先サイト)の内容については、当サイトは責任を負いませんので予めご了承ください。