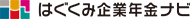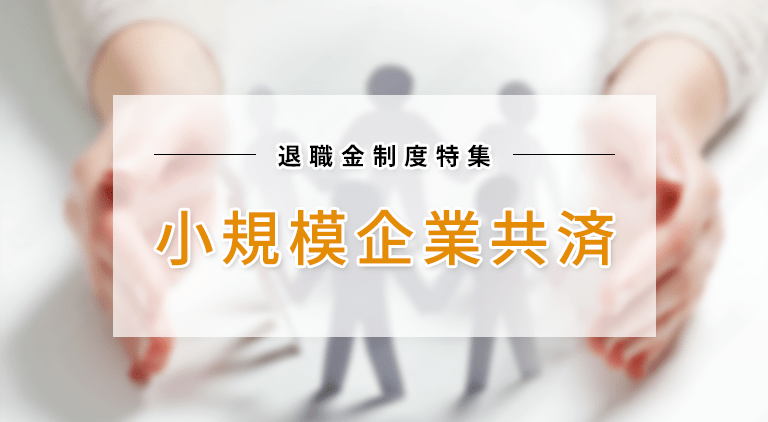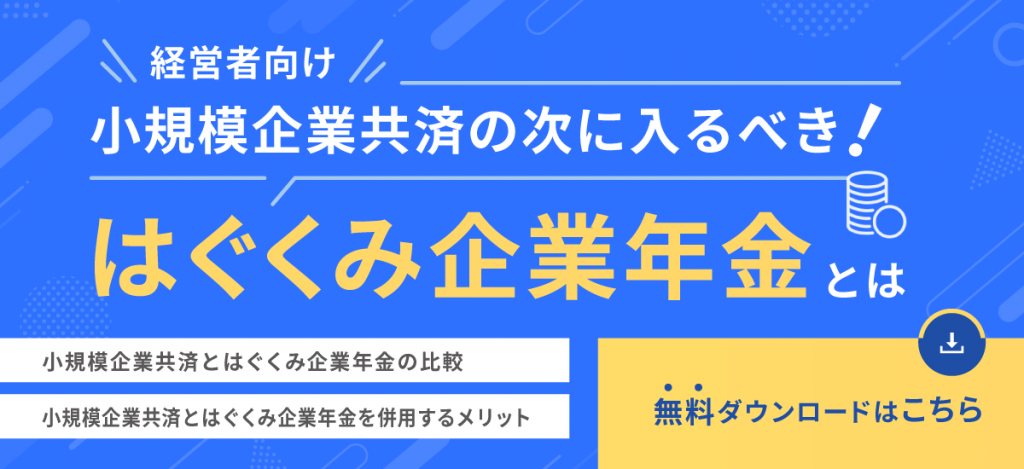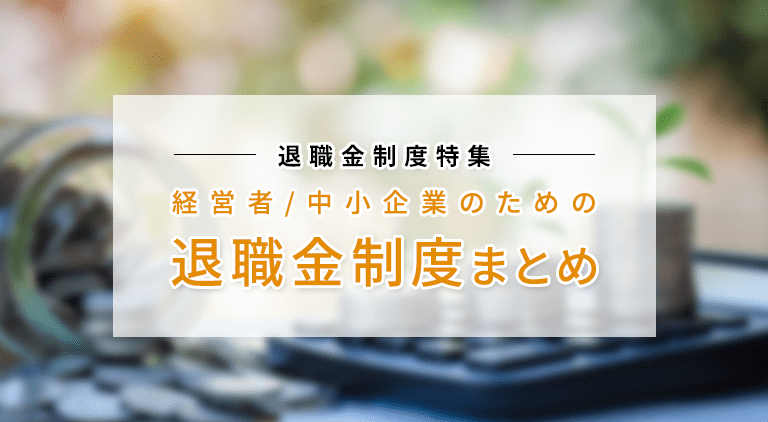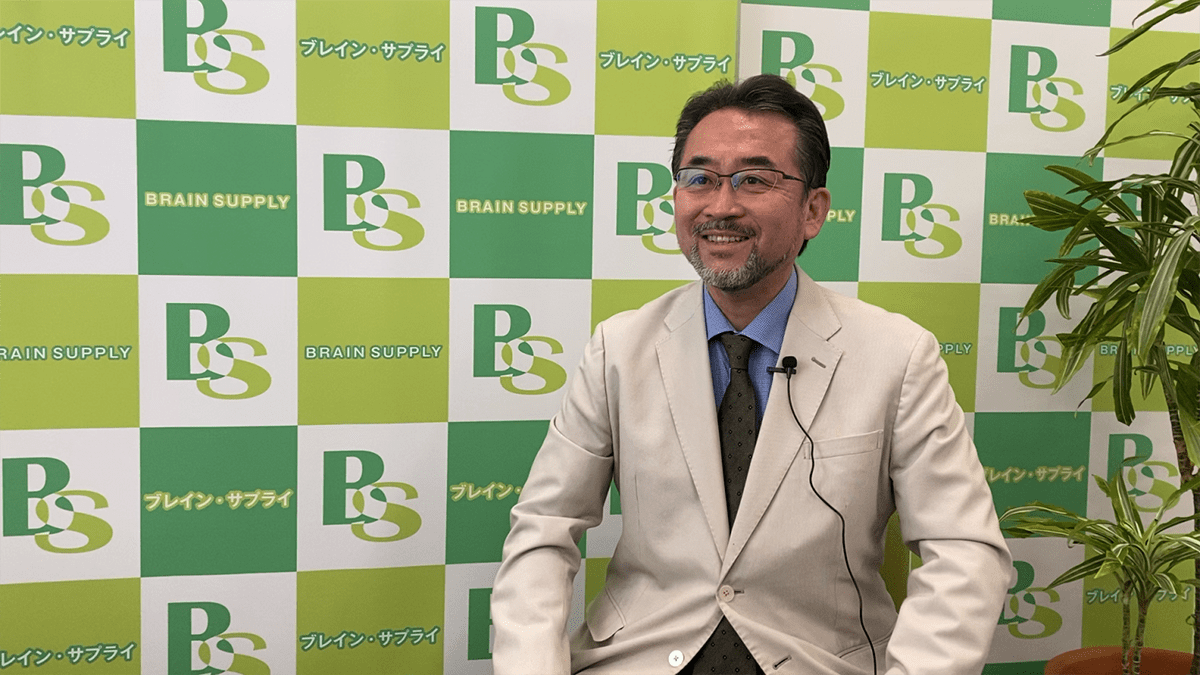フリーランス(個人事業主)や自営業者など、小規模企業経営者向けの退職金制度として「小規模企業共済」という制度があります。
小規模企業共済は、掛金が全額控除の対象になるなど税制メリットがある一方、加入期間が20年以下の場合、元本割れをしてしまうなどのデメリットもあります。
そこで本記事では、小規模企業共済の概要やメリット、デメリットについて紹介します。
※こちらのコンテンツは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構Webサイトを参照のうえ、作成しています
- 小規模企業共済の導入をご検討の方へ
- 小規模企業共済を検討中の経営者に向けた無料の資料を配信中です。
小規模企業共済の概要
小規模企業共済は、フリーランス(個人事業主)や自営業者など、小規模企業の経営者や役員が廃業や退職に備える共済制度で、1965年に発足した制度です。「小規模企業経営者の退職金制度」ともいわれています。
会社としてではなく個人として加入するものですが、掛金を積み立てていくことで、廃業や退職時、引退時にこれまでの掛金に応じた共済金を受け取れるようになります。
例えば、廃業など法人を解散した場合には「共済金A」、病気や怪我といった理由や65歳以上で役員を退任した場合には「共済金B」、これら以外の理由で退任した場合には「準共済金」を受け取れます。
運営は、独立行政法人「中小企業基盤整備機構」(中小機構)が行っています。
小規模企業共済の加入対象者
小規模企業共済には、以下の条件に該当すれば加入できます。
フリーランス(個人事業主)や自営業者など、小規模企業の経営者または役員が加入できる制度です。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※参照:独立行政法人 中小企業基盤整備機構公式サイト
加入までの手続き
小規模企業共済への加入手続きは、加入する方の立場や、加入手続きを行う窓口によって手続きが異なりますが、概ね以下の手順になります。
- 必要書類を入手
- 書類へ記入
- 窓口へ提出
- 中小機構からの書類の受け取り
必要書類について
加入する方の立場によって必要となる書類が異なり、大きく、個人事業主の場合、法人(株式会社など)の役員の場合、共同経営者の場合の3つに分かれます。
個人事業主の場合には、確定申告書の控え(税務署受付印があるものや受信通知があるもの)が必要となり、法人(株式会社など)の役員の場合には、履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本/交付後3ヶ月以内のもの)など役員登記がされていることが確認できる書類が必要となります。
詳しくは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構公式サイトのこちらのページを参照ください。
窓口へ提出について
小規模企業共済への加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行います。
加入手続きを行う窓口によって手続きが異なり、郵送による手続きはできません。
初回の掛金を現金で支払う場合は、払込区分(1か月、半年、1年)に応じた金額を持参します。
小規模企業共済の掛金について
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円~70,000円の範囲(500円単位)で自由に選択できます。
また、支払った掛金は全額所得控除の対象になります。
掛金の納付方法は、預金口座振替での支払いとなり、「月払い」「半年払い」「年払い」の3つから選択可能です。
掛金の前納も可能で、前納の場合、一定割合の前納減額金を受け取ることができます。
企業や事業主にとってのメリット
小規模企業共済は、経営者や役員、個人事業主が、個人として加入し積み立てていく制度のため、導入企業や法人としてのメリットはありません。
加入者にとってのメリット
小規模企業共済の加入者にとってのメリットは、おもに次のようになります。
メリット①:積み立てた掛金が全額所得控除の対象になる
小規模企業共済は、積み立てた掛金が全額所得控除の対象になり、掛金の分には所得税が課税されません(年間で最大84万円)。
また、掛金は月額1,000~70,000円の範囲で、500円単位で設定できます。
ただし、減額する場合には注意点があるため、後述のデメリットの項目も参照ください。
なお、独立行政法人 中小企業基盤整備機構公式サイトのこちらのページより加入した場合のシミュレーションが行えます。
メリット②:共済金の受け取りの際(解約時)、税金が優遇される
小規模企業共済は、共済金の受け取り時(解約時)にも、税金の優遇措置があります。
例えば、「共済金A」の場合(法人を解散した場合)や、「共済金B」の場合(病気や怪我で役員を退任した場合や65歳以上で役員を退任した場合)で共済金を受け取る場合、「退職所得」または「公的年金等の雑所得」扱いとなり、税負担が軽減できます。
メリット③:7つの貸付制度を利用できる
小規模企業共済の加入者(契約者)は、「一般貸付制度」や「緊急経営安定貸付け」、「傷病災害時貸付け」など、7つの各種貸付制度を活用できます。
いずれも無担保かつ保証人が不要で、利率は年0.9%~1.5%、借入期間は借入金額に応じて最大60ヵ月となっています(延滞すると年率14.6%の利子が発生します)。
- 一般貸付
- 緊急経営安定貸付
- 傷病災害時貸付
- 福祉対応貸付
- 創業転業時・新規事業展開等貸付
- 事業承継貸付
- 廃業準備貸付
小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済に加入した場合のデメリットは、おもに次の通りです。
デメリット①:約20年未満で解約すると、掛金の全額が返ってこない(元本割れになる)
小規模企業共済は、掛金の納付月数が240カ月(20年)未満で任意解約した場合、これまでの掛金合計額より少ない給付額となり、元本割れが発生してしまいます。
また、加入期間(掛金納付月数)が240カ月以上の場合でも、増額や減額など途中で掛金を変更した場合についても、任意で解約したときに受け取れる解約手当金は、これまでの掛金合計額を下回ってしまうケースがあります。
デメリット②:掛け金の減額は可能だが注意が必要
小規模企業共済は掛金を減額しようとする場合、所定の手続を行えば減額が可能ですが、減額した差額分については、その後全く運用されずに放置されることになります。
仮に、その分を解約して「解約手当金」を受け取ろうとしても、加入後約20年以上経たなければ掛金総額より目減りしてしまうため、どちらも損をしてしまうことになります。
そのため、後に減額してしまうことにならないよう、加入開始のときから無理のない範囲で掛金を設定する必要があるといえるでしょう。
デメリット③:手続きの面で手間がかかる
小規模企業共済に新規で加入しようとする場合、オンラインでできる手続きがほとんどなく、ネットバンクなどにも対応していません(2022年時点)。そのため、手続きがやや手間がかかるといえるかもしれません。
※2023年9月からマイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取れるスマホを活用したオンライン手続きが開始されました。新規申込も可能になっています。
また、2025年度から全面的なオンライサービスの開始が予定されています。
他の制度や選択肢は? おすすめ退職金制度のご案内
小規模企業共済以外の選択候補となる、おすすめ退職金制度を紹介します。合わせてご確認ください。
| はぐくみ企業年金 | 企業型確定拠出年金 | 中小企業退職金共済 | |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 確定給付企業年金法 | 確定拠出年金法 | 中小企業退職金共済法 |
| 任意加入 | 可能 | 可能 | 全員加入 |
| 加入年齢 | 70歳未満 | 70歳未満 | 制限なし |
| 加入制限 | 役員も拠出可 | 役員も拠出可 | 役員は拠出不可 |
| 税制優遇 | 有り | 有り | 有り |
| 社会保険料 | 軽減可 (※1) | 軽減可 (※2) | 軽減不可 |
| 掛金拠出 | 会社の実質的な負担を抑制 (※1) | 会社が負担 (※2)
(会社負担分は損金計上可) |
会社が負担 (会社負担分は損金計上可) |
| 拠出金 上限/月 | 1,000円~給与の20% (上限40万円) | 1,000円~55,000円 ※iDeCoと併用の場合、上限額が変わります | 5,000円~30,000円の16段階 (※3) |
| 運用 |
基金が資産を運用 |
加入者が資産を運用 | 機構(※4)が資産管理・運用 |
| 受給額 | 運用成績により変動しない | 運用成績により変動する |
運用成績により変動しない |
| 受取り | 一時金又は年金/ 退職時、休職時、 育児・介護休業時にも受取り可能 | 一時金又は年金/ 但し、原則60歳以上に制限 | 一時金又は分割払い/ 退職後に受取り可能 |
※2:「選択制」を採用した場合、軽減できることがあります。
※3:パートタイマーなど短時間労働者の場合、特例掛金月額として2,000円から可能になります。
※4:ここでは「独立行政法人 勤労者退職金共済機構」のことを「機構」といいます。
おすすめは「はぐくみ企業年金」
はぐくみ企業年金は、現在、導入企業や加入者が急増している注目の企業年金・退職金制度です。
選択制などの制度設計により、掛金拠出の会社負担を抑制できるなど、従業員、経営者、会社そえぞれにメリットが生れるとてもおすすめの制度です。
まとめ記事で11の選択肢を紹介
こちらのまとめ記事で、退職金制度の選択肢を11件まとめて紹介しています。
他の制度のメリットやデメリットを体系的に比較・検討することができます。
- 小規模企業共済の導入をご検討の方へ
- 小規模企業共済を検討中の経営者に向けた無料の資料を配信中です。
※こちらの記事は2022年6月1日時点の情報を参照の上、執筆しております。
※更新日:2024年12月/記事監修日:2024年12月17日
※当サイトからの外部参照サイト(リンク先サイト)の内容については、当サイトは責任を負いませんので予めご了承ください。